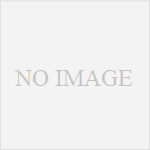40代、50代以降の女性でも取り組みやすい食事や生活習慣の改善や簡単な筋トレによるダイエットの方法を紹介します。
40代に差しかかるころから中年太りが気になってくる女性も多いと思います。
自分なりにダイエットに励んでも、なかなか効果を実感できるまでいかない方は、ぜひ参考にしてみてください。
中年女性はとても太りやすい
中年女性は太りやすいと言われています。
実はこれは年齢とともに代謝が低下してくるのが大きな原因です。
いわば老化現象のひとつですね。
代謝が低下してエネルギー消費(脂肪燃焼)が減ってきているので体質的に太りやすくなってくるのです。
中年になって急に太る人が多い?
若いころは、どちらかというと痩せ気味だったという女性も、なぜか40代前後ぐらいから太り気味なっていく人が多いという印象がありませんか?
上に書きましたように代謝が低下して太りやすい体質になってきているのに今まで通りの食事やその他の生活習慣を続けていると実際に太り気味に、いわゆる中年太りになってしまいます。
これが中年になって急に太る女性が目立つ理由です。
カギは代謝低下に対応した食事、運動
基礎代謝は10代をピークにして20代、30代、40代と年齢とともに男女とも低下し、若いころと同じ食事の内容・量、同じ運動のままでは必然的に太り気味になってしまいます。
中年太りに対応するダイエットのカギは代謝低下に対応した食事、運動ということになります。
放っておくと太ってしまうだけでなく、生活習慣病の原因にもなってしまうため、一度、食事と運動の見直しを行ってみましょう。
中年女性のダイエット 7つのポイント

ダイエットという観点で、とくに40代、50代以降の女性に気をつけてほしい食事やその他の生活習慣のポイントを7つ挙げてみました。
とくに難しいものはないと思いますが、日ごろついつい忘れがちなポイントもあります。
チェックしてみてください。
やっぱり高タンパク・低脂肪・低炭水化物が基本
代謝の低下に対応するため、食事も若いころとはに比べて内容を見直したほうがよいです。
年齢を重ねても必要なタンパク質は十分に摂ってほしいですが、脂質や炭水化物は摂り過ぎないように注意します。
脂質の多い食材や料理、米などの炭水化物は若いころよりも控えるようにします。
ながら食べは止めましょう
テレビやスマホ、DVDなどの動画を見ながら食事をしてしまうこともあると思います。
注意が食事以外のものに向いてしまうこの「ながら食べ」によって、気づかないうちに食事は、無意識に食べ物を口に運んでお腹に詰め込んでいくだけの作業になってしまいます。
気づいたらお皿が空っぽということはありませんか?
アメリカのブリガム大学とコロラド州立大学が共同で行った実験があります。
その実験は、自分の食べる音(咀嚼音)を聞きながら食べるグループと、ヘッドホンで音楽を聴きながら食べるグループに分かれ、食べたプレッツェルの量を比較するというものです。
結果は、咀嚼音を聞きながら食べたグループは平均で2.75個、音楽を聴きながら食べたグループは平均で4個食べていました。
食事にはクランチ効果というものがあり、食べる音(咀嚼音)を意識することで食べ物の摂取量を減らすことができる、過食を防ぐことができるのです。
よく噛んで(咀嚼して)食べることが食べ過ぎを防ぐことはよく知られていますが、さらに食べる音を聴くことでも食べ過ぎを防げますので、「ながら食べ」は行わず、食事は食べるものに意識を向けて、しっかり味わっていただきましょう。
骨にはカルシウム、マグネシウム
女性はある程度の年齢以上になると骨粗しょう症が気になってきます。
女性はとくに妊娠などを経て女性ホルモンのバランスが崩れて骨粗しょう症に限らず骨の健康全般ににも影響することが多いので要注意です。
骨の健康にはよく言われているようにカルシウム、マグネシウムを含む食品を摂るようにします。
夜、寝る前の食事は太る
寝る直前に食べると太るとよく言われますが、これは体内にあるBMAL1というタンパク質が影響しています。
BMAL1は脂肪を蓄積させる作用があり、活発に働くのが22時~2時と言われています。
そのため夕食は量の多い少ないに関係なく、20時~21時ごろまでには追えるようにしましょう。
取り組みやすい有酸素運動を
ダイエットのために軽い筋トレを取り入れている方も多いと思います。
筋肉を鍛えることは代謝を低下させない、あるいは高めるためにも必要です。
しかしアスリートではありませんから高負荷、長時間は無理ですし、無理して三日坊主で終わったり身体を壊してしまったら本末転倒です。
ですから筋トレを増やすよりも、取り組みやすい有酸素運動を積極的に行うことをお薦めします。
ウォーキング、ジョギング、スイミング、エアロビクスなどが代表的ですが、ストレッチやヨガなどでも十分です。
いずれも無理をせず距離や時間を少しずつ伸ばしていく意識で気軽に取り組みましょう。
睡眠不足は大敵
睡眠時間と食欲は関連していると言われています。
米スタンフォード大学が2004年に行った調査で、8時間寝た人に比べて5時間しか寝ていない人は、食欲がわくホルモン「グレリン」の量が約15%多く、食欲を抑えるホルモン「レプチン」の量が約15%低いという実験結果が出ました。
つまり睡眠時間の長さと、食欲をコントロールするホルモンのバランスが関係しているということになります。
睡眠時間が短くなるというのは起きている時間が長くなるということなので、身体はグレリンを増やしレプチンを減らすことで食欲を増進させ、睡眠不足で長くなった活動時間に必要なエネルギーを確保しようとしているのです。
最適な睡眠時間は7~8時間と言われてますが個人差があると思います。
逆に「5時間未満」は睡眠不足であるという認識は定着していますので、これより多く睡眠をとるようにしましょう。
眠り始めの3時間は目を覚まさない
基礎代謝量に影響を与えるものの一つに「成長ホルモン」があります。
成長ホルモンは睡眠中に分泌され、眠っている間に全身の細胞の新陳代謝が上昇します。
中性脂肪を分解し、筋肉の修復も行われます。これらの働きが十分に行われないと基礎代謝量が低下してしまいます。
この成長ホルモンは、睡眠の中でも眠り始めの3時間に多く出現する「特に深いノンレム睡眠」中に1日の分泌量の7~8割が分泌されます。よって眠り始めの3時間は目を覚ますことがない工夫をしてみましょう。
また成長ホルモンは空腹時に分泌されやすいので、空腹の状態で眠り始めの3時間を迎えるようにします。
お腹いっぱいの状態で就寝するようなことは避け、就寝の2時間前までには食事を終えるようにします。
中年女性もムリなく痩せる!6秒筋トレ

ダイエットに取り組んでいる女性の中には単純に体重を減らすだけでなく、代謝を落とさない、あるいは代謝を上げるために筋トレも取り入れている人も多いと思います。
しかし若い人のようなハードな筋トレは難しいと感じているのではないでしょうか?
そんな方にも無理なくできるのが「6秒筋トレ」です。
6秒筋トレはアイソメトリックスがベース
美容研究家の境貴子さんが考案した6秒筋トレは、“アイソメトリックス”という筋肉トレーニングがベースになっています。
アイソメトリックスは、お腹を力いっぱいへこませるなど、鍛えたい筋肉に思いきり力を入れてキープすることで、筋肉に負荷を与えるトレーニング方法です。
筋肉を伸ばしたり縮めたりして鍛える従来からのトレーニングとはかなり違います。
アイソメトリックスの特徴
アイソメトリックスを応用した6秒筋トレは、1回6秒と短時間で単純な動きのうえに、激しい動きではないので、運動が苦手な人、高齢者など運動ができない人やリハビリにも活用されているほどです。
ただ短時間とはいえ正しく行えば筋肉痛にもなるくらいで、効果もしっかり期待できます。
6秒筋トレの3大ポイント
短時間でしかも単純な動きの6秒筋トレですが、守ってほしいポイントが3つあります。
1.息を留めずに呼吸を続ける
筋肉に力を込めるときは普通はつい息を止めてしまいがちです。
しかし呼吸を止めて力を入れると血圧が急上昇したり心臓に負担がかかったりして危険を伴います。
筋肉に力を込めるときは息を留めずに呼吸を続けてください。
2.鍛える筋肉の部分に意識を集中する
アイソメトリックスに限らず筋トレ全般で「鍛える筋肉を意識する」ことは重要なポイントになります。
とくにアイソメトリックスで行うことは、その部分の筋肉に集中して力を込めることだけですから、行っている最中は今鍛えている筋肉の部分に意識を集中することで筋トレの効果を高めるようにします。
3.力を入れたあとは必ず緩める
筋肉を効率よく刺激するには筋肉に力を込める、緩めるをメリハリをつけて行うのがよいです。
6秒間力を入れて硬くなった筋肉は、6秒間かけて力を緩めていきます。
6秒筋トレ法は、筋肉の中にある「筋繊維」に一時的にダメージを与え、修復しようとする「自己回復力」を最大限に利用した筋トレなので、毎日ではなく1日置きに行ってください。
まとめ
年齢を重ねるにつれて人はどうしても太りやすい体質になりがちです。
でも食生活や生活習慣を見直し、そこに軽い筋トレを加えるだけで中年太りも予防、改善することができます。
この記事で紹介した内容を参考にあなたもチャレンジしてみてください。
なおダイエットと食事や筋トレの関係については下の記事でも説明しています。
併せてお読みください。
⇒ ダイエットは運動後の食事が決め手! 摂るべき4つの栄養素
⇒ 筋トレは食事前?食事後?3つのポイントで効果的に筋肉をつけよう!
この記事が参考になったらシェアお願いします。これからも役立つ記事を書いていきます。