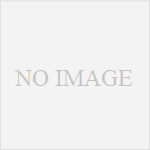永代供養をするには、位牌や仏壇はどうするべきなのか、分からない方は多いと思います。
近年では、跡を継ぐ者がいなくなり、永代供養をすることも増えてきている中、位牌や仏壇の供養や処理の正式な仕方が伝わっていないということがあります。
ここでは、永代供養の後に位牌と仏壇をどうするべきかご紹介しています。
永代供養とするなら位牌と仏壇は

位牌の永代供養をする場合は、寺院などで長い期間の10年~20年位牌を預かり管理してくれます。
これには、事前にまとまった金額を払う必要があります。
そして、期間が終了したら、寺院でお焚き上げされ処分されることになります。
近年では、お墓の永代供養の際に、位牌も一緒に預かってもらうこともできる場合があります。
それは寺院によって違いますので、一度問い合わせてみた方が良いでしょう。
お墓を永代供養しても、家庭で位牌に手を合わすくらいはしたいということであれば、位牌を手元に残しておくこともできます。
また、位牌の一時預かり供養というのもあって、一定の期間だけ寺院などで預かってもらい、その期間が終わる頃に、位牌を手元に残すか、お焚き上げをして処分をするかの2択を選ぶというのがあります。
仏壇については、継承者がいない場合や、嫁いだ先での仏壇で供養を続けるという場合は、お正念を抜く、つまり仏壇から魂抜きをしてもらうために、宗呂にその旨のお経を唱えてもらえば、単なるゴミとされますので、処分が出来ます。
まだ子などの継承者が存在するなら、仏壇は処理できません。
日本の法律で「祭祀財産」として相続することになるのです。
お正念抜きするのは
お正念抜きは、他にも言い方があって、お精根抜きや、お性抜き、魂抜き、御霊抜き、など、様々な呼び方をする場合があります。
地域によって呼び方があるようですので、これらの呼び方を覚えておき、同じ意味だということも理解しておくと良いでしょう。
お正念抜きをするのは、先に述べたように、継承者がいなくて位牌や仏壇を処理するときや、お墓を動かしたり戒名を彫刻したりする場合に行われます。
つまり、位牌や仏壇、お墓に仏様やご先祖様がいらっしゃるのに、勝手に動かしたり加工したり処分したりすることを避けるべきだということから、正念抜きが行われるということなのです。
まとめ

いかがでしたか?永代供養をしたからといって、すぐに位牌や仏壇まで処理してしまうわけではないことが分かりますね。
継承者が存在する場合は、むやみに永代供養するわけでもありません。
永代供養とは、継承者がいないから、代わりに寺院などで供養をお願いするということなのです。
本来引き継いでいくべき血縁者がいるのなら、大切な方が亡くなったこと、仏様をきちんと供養してあげたいものですね。
なお永代供養にかかる費用については別記事にまとめています。
ぜひ確認してください。
また永代供養に近い樹木葬の位牌については下の記事で説明しています。
併せて参考にしてください。
この記事が参考になったらシェアお願いします。これからも役立つ記事を書いていきます。