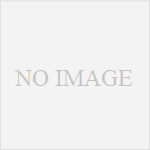松の内が過ぎたころ、1月11日に鏡開きをして、お餅を「ぜんざい」にして食べるという風習がありますが、なぜそのような風習が現在も続いているのでしょうか?
確かにおいしいですが、他にも食べ方がありますよね。
ここでは、その由来や、呼び名について、鏡餅の開き方などをご紹介しています。
鏡開きで「ぜんざい」にする理由とは

鏡餅を「ぜんざい」にする理由は、小豆がキーポイントになっています。
小豆は、古来から魔除けとして邪気を払う効果があると言われており、その赤色も魔除けの色として扱われてきたのです。
鏡餅は、歳神様の力が宿っているので、邪気を払う小豆と鏡餅の組み合わせが、最高に縁起の良い、無病息災も願う気持ちも込められた食べ方とされたのです。
「ぜんざい」と「しるこ」という呼び名
「ぜんざい」という呼び名は、出雲地方で神在餅からきており、これが次第に、「ずんざい」、「ぜんざい」という具合に呼ぶようになったと言われています。
よく、「ぜんざい」と「しるこ」の違いって何?と思う人も多いと思いますが、地域によって、呼び名がバラバラなので混乱する原因になっています。
関西地方では、「ぜんざい」は汁気のある粒あん、「おしるこ」は汁気がありこしあん、関東地方では「ぜんざい」は汁気がないもの、「おしるこ」は汁気があるものというように、地域によって呼び名が違っています。
これでは、もし関東の人が関西で「ぜんざい」を注文したとしたら、まるで違うものが出てきてしまうということになりますね。
地域によってこんなにも違いがあるのは、日本の風習の面白さでもあります。
鏡餅の鏡開きについて
鏡餅は切ってはいけないとされています。
これは、切腹を連想させる行為という理由からきています。
また、割るというのも縁起が良くないと言われ、開くという言い方になっています。
そこで、ハンマーなどで叩いて開くということですが、それだと均等に出来ずに、大きさもバラバラになってしまいます。
ずっと飾っておいたり、保存していた鏡餅は、カチカチになっているので、分けるのは一苦労ですね。
それより、もっと簡単に分ける方法があります。
鏡餅を水でくぐらせ皿に乗せて、ラップをしてレンジで温めます。
こうすれば、柔らかくなり簡単に分けられるようになります。
まとめ

いかがでしたか?
何気なく1月11日に鏡餅を「ぜんざい」にして食べていたかもしれませんが、無病息災を願う、邪気も払ってくれるなどという、案外古来からの深い由来からきていたものだったのです。
今後は、風物詩として楽しむこともプラスして「ぜんざい」を美味しく食べることが出来るのではないでしょうか。
また、鏡餅をレンジでチンするなら、かなり熱いので、やけどに注意して美味しく召し上がってくださいね。
あと七草粥(ななくさがゆ)や正月飾りの処分については下の記事を参考にしてください。
⇒ 正月飾りの処分は神社で行うのが基本です。知ってましたか?
この記事が参考になったらシェアお願いします。これからも役立つ記事を書いていきます。