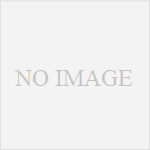1月7日に七草粥(ななくさがゆ)を食べる風習がありますが、なぜそのような風習が広まり、そしてなぜその時期に食べられるようになったのでしょうか。
年末年始のごちそうの続いた胃を休めるためにそのタイミング、というのもあるかもしれませんが、古来からの七草粥の由来と意味などをご紹介いたします。
七草粥の意味と由来は
七草粥を食べる習慣は、「人日の節句」という5節句の1つとして1月7日に食されたことに由来します。
5節句とは、1年に5回ある節日のことで、1月7日、3月3日、5月5日、7月7日、9月9日の日にあたります。
この中の1月7日は、中国では人を大切にする日として「人日」と呼び、唐の時代に無病息災を祈る7種類の野菜を入れた汁物の「七種菜羮」という風習がありました。
これが日本に伝わって、「七草粥」に変化し、現在の日本でその年は万病にならずに元気に過ごせるという意味になりました。
これに入る七草は、古来日本で若菜摘みが行われていて、年の初めに野に目を出した草を摘み取ったものでした。
七草粥に使われる七草とは

七草粥には、春の七草を粥にしたもので、芹(せり)、薺(なずな)、御形(ごぎょう)、繁縷(はこべら)、仏の座(ほとけのざ)、菘(すずな)、蘿蔔(すずしろ)の7種が入っています。
この呼び名は、現代では使わなくなった呼び名もあるので、聞いたことがないという方もいると思います。
各々に込められた意味と効果などを以下にまとめてみました。
- 芹は、食欲増進になり、競りに勝つ
- 薺は、別名はぺんぺん草、撫でて汚れを取り除く
- 御形は、母子草のことで、痰や咳に効く、仏体
- 繁縷は、「はこべ」とも呼ばれ、昔から腹痛薬として胃炎などに効果があります。繁栄がはびこる
- 仏の座は、胃を健康にし、食欲増進に、仏の安座
- 菘は、蕪のことで、整腸作用の効果や消化を促進し、しもやけそばかすに効果があり神を呼ぶ鈴と言われています。
- 蘿蔔は、大根のことで、風邪予防と美肌に導く効果、汚れのない清白
このように、七草は胃腸に優しく、風邪にも良い効能があると言われていますので、暴飲暴食などの続いた年末年始の胃腸の疲れには、ちょうど良い料理と言えます。
まとめ

胃に優しい七草粥ですが、古来より言い伝えから、人を大切にする日であり、万病を防いでくれる、というのが現在まで続いている理由ではないでしょうか。
現在では七草というと単にお正月に七草粥を食べるという風習を指すというイメージになっていますが、日本の風物詩の1つとしてとらえてみてはいかがでしょうか。
なお鏡開きの由来や正月飾りの処分については別記事で説明しています。
⇒ 正月飾りの処分は神社で行うのが基本です。知ってましたか?
この記事が参考になったらシェアお願いします。これからも役立つ記事を書いていきます。