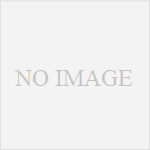5月5日といえば「こどもの日」。端午の節句とも言いますよね。
毎年この時期になると、男の子がいる家庭では兜などを飾って、子どもの健やかな成長を願うものです。
でも、この兜を飾るタイミング、意外と悩むものですよね。
いつから飾ればいいのか?決まりはあるのだろうか?など、疑問はつきません。
そこで今回は、こどもの日ではいつから兜を飾るのがいいのかということと、子どもの日に兜を飾る意味を併せて紹介します。
こどもの日 兜を飾るのはいつからがベスト?

子どもの日の兜を飾るタイミングですが、特に決まりはありません。
できるだけ早く飾った方がいいとする地域や、子どもの日の1週間前に飾るという地域もあります。
ですが、兜には「先手必勝」という意味もあるので、できるだけ早く飾った方が良いと言われています。
というわけで、春分の日(3月21日)を過ぎたら飾るという人が最も多いです。
彼岸入りした頃でもありますし、女の子がいる家庭では、ちょうどひな人形を片づけた時期なので、ベストなタイミングと言えますよね。
このように、兜を飾るタイミングには色々な考えがあります。
しかし、遅くても4月下旬までには飾るようにしましょう。
初節句ならば、できるだけ長い時間飾りたいので、3月下旬がおすすめですよ。
ちなみに、兜を飾るのは床の間がベストと言われていますが、床の間のない家はリビングなどに飾ってもOKです。
その場合は、日当たりのいい場所に飾るようにしましょう。
飾る方角に決まりはありませんが、北向きは避けるようにしてくださいね。
兜をしまう時期にも特に決まりはありませんが、5月中旬頃に片づけるのが一般的と言われています。
あまり知られていない!こどもの日に兜を飾る意味
子どもの日に兜を飾る。男の子のいる家庭では、毎年当たり前のように行われていることですが、これは武家社会の風習が基になっています。
室町時代末期の端午の節句(こどもの日)では、虫干しを兼ねて旗指物を飾る風習がありました。
その後、鎌倉時代になると武家社会が成立し、端午の節句(こどもの日)には、男の子が武士として強くたくましく成長することを願うという意識が色濃くなっていきます。
この頃、外には旗幟(きし)と言われる旗印を立て、座敷に鎧や兜などの武具を飾るようになりました。
鎌倉時代には、身の安全や志が叶って神社にお参りする時に、鎧や兜を奉納するというしきたりがあったことも、端午の節句(こどもの日)に兜を飾る風習に繋がったと言われています。
武家社会の風習であったこどもの日が、広く定着したのは江戸時代。
江戸時代の庶民が武家社会の風習を真似たことがきっかけとされています。
武将にとっての鎧や兜は、自分の身を守るための大切な道具でした。
このことから、鎧や兜は「命を守る象徴」と考えられ、「男の子を事故や病気、災害などから守ってくれますように。」との願いを込めて、飾られるようになったのです。
ただ、庶民は本物の鎧や兜を持っていなかったので、作り物の鎧や兜を飾っていました。
それが現代にも受け継がれているというわけなのです。
まとめ

こどもの日には、男の子の健やかな成長を願って兜を飾ります。
いつから兜を飾るかということに、特に決まりはありませんが「先手必勝」という意味合いもあるので、できるだけ早く飾りましょう。
地域差がありますが、彼岸入りした春分の日あたりに飾る人が最も多いです。
兜を飾る風習は、もともとは武家社会の風習でした。
それを江戸時代の庶民が真似たことで、現在のように「こどもの日に兜を飾る」風習が定着したのですね。
命を守る象徴でもある兜、毎年飾って男の子の健やかな成長を願いましょう!