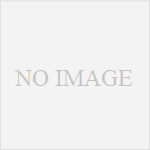寝不足が続いたりすると、ふとしたときに目眩(めまい)を感じることがありませんか?
でも睡眠不足でどうして“めまい”が起きるのでしょうか?
対処はどうしたらいいの?
さらに“めまい”の原因は睡眠不足だけとは限りません。
今回の記事では“めまい”など睡眠不足で起きる症状と対処、日常の生活で気をつける内容について説明します。
この記事を参考に、あなたも健康で快適な生活を取り戻してください。
“めまい”の原因は睡眠不足だけじゃない

ひと言で“めまい”と言っても、その症状から大きく分けて3種類の“めまい”があります。それぞれ原因も違います
目の前が真っ暗になる“めまい”
急に立ち上がったり、お風呂で湯船から出ようとしたときに、さーっと血の気が引くように頭がクラクラしたり、一瞬目の前が真っ暗になることがあります。
いわゆる「立ちくらみ」のような状態になります。
耳や脳に異常はなくても脳に送られる血液の量が一時的に不足することで起きます。
貧血や過労、ストレスなど自律神経のバランスが乱れると起きやすと言われています。
低血圧や不整脈でも起きるようです。
起立性低血圧、立ちくらみ様めまい、眼前暗黒感などとも呼ばれます。
フワフワする“めまい”
地に足が着かないような雲の上を歩いているような感じのフワフワした“めまい”(浮動性めまい)や、足元がフラフラして地面が揺れるような“めまい”(動揺性めまい)があります。
ストレスなど以外に、両側の内耳や脳の障害によって起きることもあります。
グルグル目が回る“めまい”
自分自身や、周囲の景色や壁、天井などが急にグルグル回ってるように感じます。
「回転性めまい」とも呼ばれ、極度に酔った状態と似てます。
三半規管など主に内耳の異常が原因とされ、嘔吐を伴うこともあります。
メニエール病の代表的な症状です。
睡眠不足による“めまい”
寝不足で起きる“めまい”は、目の前が真っ暗になる“めまい”か、フワフワする“めまい”が多いです。
寝不足になると交感神経と副交感神経のバランスが崩れ、自律神経に乱れが生じますので、血行が悪くなり、血圧が下がりやすくなり、目の前が真っ暗になる“めまい”が起きやすくなるのです。
同様にストレスも溜まりやすくなりますので、フワフワする“めまい”も起きやすくなります。
めまいが起きた時の対処法
では“めまい”が起きた時にはどうしたらよいでしょうか。
一番大事なのは慌てないことです。
まずその場ですぐにしゃがみ込むます。
できれば座ったり横になったりして、しばらく休みます。
転倒してケガをすることを予防する意味もありますが、頭の位置を下げることによって脳への血液循環を促して血圧を戻し意識をハッキリさせる効果があります。
可能なら短い時間でも昼寝をすれば寝不足による不調がかなり改善されます。
睡眠不足による症状は他にも
寝不足が続くと“めまい”のほかにも影響が表れてきます。
- 日中の眠気、疲れ
- ストレスの増加
- ストレスを受けた脳内血管の拡張による頭痛(偏頭痛)、耳鳴り
- 身体全体の機能の不調による吐き気
- 食欲不振、あるいは逆の食べ過ぎ
- 細胞を修復する機能の低下により肌質が悪化
- 脳の疲労による記憶力、思考力、集中力、注意力の低下
- 精神の不安定化、うつ病のリスク
睡眠不足による影響については下の記事でも説明しています。
参考にしてください。
手っ取り早い眠気覚ましの方法
上に書きましたように種々の影響が考えられますので、睡眠不足の状態を放置しておくのは危険です。
このところ寝不足気味と感じているときに睡眠不足とその影響を手っ取り早く解消する方法をいくつか挙げておきます。
カフェインの摂取
眠気覚ましにコーヒー、緑茶などを飲む人は多いと思います。
ご存知のようにコーヒーや緑茶、あるいはエナジードリンクなどにはカフェインが含まれていて、カフェインは血液に採り込まれてから約30分で脳に到達し10時間ほど効果が続くと言われています。
ただしカフェインは習慣性があり、日常的に飲み慣れていると効果が薄くなってくる傾向があります。
ガムを噛む
ガムを噛むことで顎の筋肉が活発に動き、それが脳を刺激するので、血液の循環が良くなって眠気を覚ます効果があります。
ほかにもガムの種類によって、ミント系など味付けによるスッキリ爽やか感やカフェインの配合などによる眠気覚まし効果もあります。
冷水で顔を洗う
近くに洗面できる場所があれば、冷水で顔を洗うのが効果的です(潜水反射効果)。
顔に冷たい水の刺激が加わることで脳や心臓に血液が集まり、働きが活発になることで目が覚めてきます。
ツボを押す
もしツボの場所を知っているのであれば、この方法が最も手軽にできます。ここでは3つ紹介します。
- 手の中指の爪の生え際から2㎜ほど下、第一関節付近の人差指側にある中衝(ちゅうしょう)と呼ばれるツボを、反対の手の親指と人差指で強くつまんで揉みます。
- 手のひらの真ん中にある労宮(ろうきゅう)と呼ばれるツボを、反対の手の親指で強めに刺激します。
- 手の甲を上にして親指と人差指の骨が交差する場所のくぼみにある合谷(ごうこく)と呼ばれるツボを反対の手の親指で強めに刺激します。合谷は「万能のツボ」と呼ばれ眠気覚ましだけでなく全身に幅広い効果があります。
仮眠をとる
時間的に場所的に可能であれば仮眠をするのが一番です。
本格的な眠りに入らないように15分~20分程度に収めるのがコツです。
睡眠不足を解消して健康的な生活を送る方法
多忙な生活が続いて一時的に寝不足になっている状態であれば、眠ることによって改善しますが、慢性的な睡眠不足、時間があっても眠れないなどの場合は、身体のリズムから改善していく必要があります。
夜に眠れるための習慣付け
人間の身体は朝起きて太陽の光を浴びることで1日の活動を開始するようにできています。
脳の体内時計がリセットされて「睡眠ホルモン」とも呼ばれるメラトニンの分泌が止まり、1日の活動がスタートするのです。
そしてこのメラトニンは、その後14~16時間ほど経過すると、体内時計からの指令により再び分泌を始めます。
分泌が進むにつれ深部体温が低下し眠気を感じるようになります。
慢性的な睡眠不足や「眠れない」状態が続くのは、上に書きました身体のリズムが崩れているということですので、このリズムを元に戻し眠りの改善を目指します。
ポイントは朝起きたら光を十分に浴びることです。
不眠治療の光療法の原理ですが、これを続けることにより睡眠のリズムが正常になっていき、夜に自然に眠くなるようになります。
この光は太陽の自然光でよいですし、蛍光灯などの人工の光でもよいです。
時間にして30分~1時間程度、光を浴びるようにします。
快眠につながる栄養素
上で書きましたメラトニンの分泌量は子ども時代にピークに達し、その後は年齢とともに減少していきます。
メラトニンの元となる必須アミノ酸のトリプトファンは肉類、魚介類をはじめとして多くの食品に含まれていますので、日ごろからバランスのよい食事を心がけます。
トリプトファンを含むサプリメントなども広く販売されていますが、食事から摂取することを基本としましょう。
まとめ

めまいの原因は色々ありますが、睡眠不足からくる身体の不調もそのひとつです。
仕事が忙しいときなど一時的な対処で眠気を覚ますことも必要ですが、基本的には日ごろから毎日の身体のリズム、バランスのとれた食事を心がけ、十分な睡眠のとれる生活を目指していきましょう。
睡眠の質を上げる方法については下の記事で説明しています。ぜひ参考にしてください。