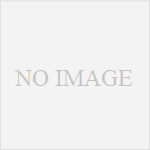親の介護は、突然やってくるかもしれません。
その時に兄弟とうまくやっていけるのでしょうか。
どの家庭にもその問題はいつか発生する可能性があります。
親の介護が必要になる時までに、事前にしておいた方が良いことや、兄弟と役割分担の仕方をご紹介いたします。
ぜひ参考にしてください。
親の介護を兄弟とも話す

普段仕事や日々の生活をしていると、親の介護がいつか発生することに目を向けていないのではないでしょうか。
いざ、親の介護が始まったら、いつまで続くのか分からないなか、兄弟でうまくやっていかなければ、親も兄弟も生活が成り立たなくなってしまいます。
そのために、事前にしておくべきことがあります。
親が元気なうちから、もし介護が必要になったらどうしたいか、兄弟にどうしてほしいか、話し合う必要があります。
倒れてしまってからでは、まともに話が出来ない場合、親の希望が分からずに闇雲に介護を続けることになります。
また、兄弟同士でも定期的に介護について、各々何が出来て、金銭的にはどうやって分担するのかなど、話し合うことが大事です。
兄弟でしっかり話し合うことで、実際に介護が始まった時、揉めずに進めることが出来るでしょう。
近年の社会現象による兄弟の介護の仕方
近年では、核家族化、晩婚化、共働きなどの事情の絡みなどから、兄弟だけで介護を続けるのは困難な場合が多いと思います。
もちろん、自分の親なのだから、血のつながった兄弟で面倒を見てあげたい、と思うのは素敵ですが、その思いだけではどうしてもやっていけません。
がんばって介護を続けても、いつか兄弟の方が倒れてしまいます。
それだけ、介護は体力や精神を消耗してしまうのです。
介護が必要になったら、まず、同居など一番近くにいる兄弟が主介護者になることをお勧めします。
これは、その主介護者だけが介護をするというわけではなく、介護施設や兄弟との打ち合わせのやり取りを主でする、ということです。
親の介護の窓口というわけです。
同居している兄弟は、介護施設にケアマネージャとのスケジュール調整をし、離れて住んでいる兄弟とは、週末に来てもらい介護のサポートをしてもらったり、金銭的に協力してもらうなど、具体的に管理していくのです。
親の介護は、1人でするのではなく、兄弟や周りの協力で成り立つのです。
まとめ

親の介護は必ずしも兄弟だけで見るというわけではありません。
介護の仕方も分からないのに、突然介護をスタートしても、親にとっても居心地が悪いものになってしまうでしょう。
また、同じ親から生まれた兄弟なのに、介護により揉めて、亀裂が入ってしまうのもとても悲しいことです。
親の介護についてきちんと話し合って、介護施設を利用しながら力を合わせて乗り切りましょう。
なお親御さんが遠くに住んでいる場合は、また別の配慮が必要になります。
下の記事も併せてご確認ください。