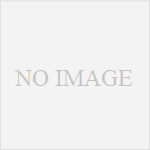毎年2月14日はバレンタインデー。
バレンタインデーといえば、女性が想いを寄せる男性にチョコレートを渡す日として知られています。
それ以外にも、好意がなくてもチョコを渡す「義理チョコ」や、女性同士でチョコを渡し合う「友チョコ」、さらには男性が女性にチョコレートを渡す「逆チョコ」なんていう言葉もあるぐらいで、幅広い年代が楽しむことのできるイベントとして定着していますよね。
今回は、そんなバレンタインデーの由来と、日本ではいつ始まったのかを紹介します。
バレンタインデーの由来、日本ではいつ始まった?

そもそも、日本でバレンタインが始まったのはいつなのでしょうか。
日本でバレンタインデーが始まったきっかけとされる説には4つあります。
1つ目は、昭和11年に洋菓子店のモロゾフ株式会社が、「バレンタインデーにチョコレートを贈る」ということを提唱したとする説です。
2つ目は、昭和33年にメリーチョコレートカンパニーが伊勢丹新宿本店で、バレンタインセールを行ったとする説です。
3つ目は、昭和35年に森永製菓がバレンタインデーの新聞広告を出したとする説です。
そして4つ目が、昭和44年にソニープラザがチョコレートを贈ることを流行らせようとしてできたという説です。
諸説ありますが、企業が商業目的で広めたことが始まりです。
「バレンタインデーはお菓子業界の陰謀」という言葉を聞いたことがある人も多いと思いますが、あながち間違いではないようですね。
そして1970年代に、現在のように「バレンタインデー=女性が好きな男性に想いを伝える日」として定着したと言われています。
バレンタインデーが「恋人たちの日」になった由来
では、なぜバレンタインデーが、好きな人に想いを伝える「恋人たちの日」となったのでしょうか?
実はここには驚きのエピソードがあるのです。
バレンタインデーは、英語で「Saint Valentine’s Day」と言います。
これを日本語訳すると、「聖バレンタインの日」という意味になります。
このバレンタインとは、古代ローマ時代に殉教したバレンタイン司祭を指します。
バレンタイン司祭は、当時、「士気が下がる」とされて禁止されていた兵士の結婚を認め、結婚式を行っていました。
しかし、皇帝にそれを知られてしまい、兵士の結婚式を行うことをやめるように命令されましたが、それを拒否したために捕えられ、処刑されました。
そのバレンタイン司祭が処刑された日が2月14日でした。
当時のローマでは、2月14日は、家庭と結婚の女神であるユノの祝日とされていました。
翌日の2月15日は、豊年を祈るルペカリア祭りの始まる日で、別々に住んでいる男女は、札を引いてペアとなり、祭りの間はパートナーとして過ごすことが定められていたそうです。
札を引いてペアとなったことがきっかけで、恋に落ち、祭りが終わった後に結婚する男女が多かったことから、ルペカリア祭りは「カップルを生む祭り」として知られるようになりました。
そんなルペカリア祭りの前日で、バレンタイン司祭が処刑された日でもある2月14日は、キリスト教徒にとっても祭日となり、「恋人たちの日」とされるようになったのです。
まとめ

現在では、想いを寄せる男性にチョコレートを渡す日とされているバレンタインデーですが、クリスマスと同様、本来はキリスト教徒に重要とされた日が、日本では企業の商業目的で広がったのですね。
でも、きっかけはどうあれ、バレンタインデーに想いを伝えることができ、カップルを生み出してきたのも事実。
最近は、「友チョコ」や「ご褒美チョコ」など、好きな人がいなくても、イベントとしてバレンタインデーを楽しむことができるようになってきました。
シチュエーションに合わせて楽しいバレンタインデーを過ごしてくださいね!
なお、どんなプレゼントを贈ればいいのか迷ったら、下の記事も参考にしてください。
この記事が参考になったらシェアお願いします。これからも役立つ記事を書いていきます。