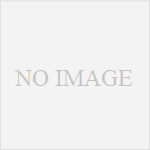毎年ひな人形を飾るのもそうですが、定番のちらし寿司も楽しみの一つだったのではないでしょうか。
でも、どうしてひな祭りにちらし寿司なのか気になりませんか。
今回、ちらし寿司がひな祭りの定番になった理由や、ちらし寿司の由来を調べました。
ひな祭りに ちらし寿司を食べる由来は?

ちらし寿司はお祝いの席で食べるイメージがありますよね。
寿司という言葉には、寿が祝う、めでたいこと、司が意味する、由来する、という意味が込められていて、祝うことを意味する食べ物ということになります。
このことから、ひな祭りはお祝いの席であるので、ちらし寿司が食べられるようになったということです。
所説あるとは思いますが、そこまでの深い由来ではないのかもしれません。
ただ、ちらし寿司に入っている具材には、それなりの由来があるようです。
エビは、腰が曲がっているので長生きの象徴とされます。
菜の花は、春らしさを感じることが出来ます。
レンコンは、将来の見通しがきく、豆は健康でまめに働けるということ、ゴボウは細く長くしっかり根を張ります。
にんじんは、赤い色が寿をあらわすということです。
他のお寿司に比べて、たくさんの縁起の良い具材が入っているので、お祝いの席ではちらし寿司が選ばれるようになったのです。
また、ちらし寿司はたくさんの具材が入っていることから、将来的に食べ物に困らずに幸せに暮らせるようにという説もあるとも言われています。
ひな祭りは将来幸せな結婚が出来るようになってほしいという願いがこもった風習でもありますから、ちらし寿司を食べるのがピッタリですよね。
親が子の健康と幸せを願うことがちらし寿司に込められているのでしょう。
ちらし寿司の由来は
ちらし寿司そのものの由来としては、一汁一菜令という説があると言われています。
岡山県、当時の備前で大洪水があった際に、藩主池田光政公が町の復興を早めるために出したのが一汁一菜令だったのです。
それは、汁物一品と副食一品以外を禁止するというもので、ぜいたくを抑制するものでした。
そこで庶民が、たくさんの具材を寿司飯に入れ込んでしまえば、おかずではないだろうという解釈をして、ちらし寿司が編み出されたようです。
これが、ちらし寿司の原型だったのです。
まとめ

いかがでしたか? ひな祭りにちらし寿司を食べる由来は、とくに深いものではなさそうでしたね。
でも、ちらし寿司自体は大変縁起の良い食べ物であるし、ぜいたく禁止の令から生まれた偶然の産物ともいえる面白い昔のエピソードでしたね。
せっかくのひな祭りですから、ぜいたく禁止なんて言わないでちらし寿司で華やかにお祝いしてあげてくださいね。
なお、ひな祭りには他にも一般にはあまり知られてないことがあります。
下の記事も参考にしてください。