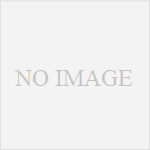3月3日といえば女の子の節句、ひな祭りですよね。
ひな祭りは女の子の健やかな成長を願う大切な行事です。
ひな祭りの食事といえば、ちらし寿司やハマグリのお吸い物、菱餅などがありますが、正しい意味を知っている人は多くありません。
女の赤ちゃんなら3月3日に初節句を行いますよね。
赤ちゃんの人生のためにも、ひな祭りの食事に込められた意味を知ってお祝いをするようにしましょう。
ひな祭りに雛人形や桃の花を飾る理由も併せて紹介します。
ひな祭りの食事 こんな意味があった!

ちらし寿司やハマグリのお吸い物など、ひな祭りは女の子の節句というだけあり、色鮮やかな食べ物が並びます。
これらの食事、実は華やかさだけではなく、1つ1つにきちんと意味があります。
ここでは4つの食べについて、その意味を詳しく紹介します。
意味を知った上で、願いをこめてお祝いをしたいですね。
ちらし寿司
1つ目はちらし寿司ですが、ちらし寿司というより、ちらし寿司に入れる具に意味があります。
ちらし寿司に入れる具として代表的な物に、エビと豆、レンコンがあります。
エビは長生き、豆は健康、レンコンは見通しが効くという意味合いがあります。
縁起のいい食べ物を具に入れることにより、「健やかな成長と充実した人生」を願うのですね。
ハマグリのお吸い物
2つ目はハマグリのお吸い物です。
なぜハマグリなのかというと、ハマグリの貝殻は対になっているものがピタリと合うことから、良縁の夫婦を象徴しています。
ハマグリのお吸い物には、「良縁に恵まれ、一生一人の人と添い遂げられるように」という願いが込められています。
菱餅
3つ目は菱餅です。
菱餅は緑と白、ピンクの層のあるひし形のお餅ですが、それぞれの色と形に意味があります。
菱餅の緑は「健康や長生き」を、白は「清浄」を、ピンクは「魔除け(厄除け)」を意味しています。
また、緑の餅は血液を増やす働きのあるヨモギで着色してあり、白い餅には血圧を下げる働きのあるひしの実が使われています。
そしてピンクの餅は解毒作用があるクチナシで色付けされているなど、健康面でもきちんと意味があります。
菱餅がひし形をしているのにも理由があり、ひし形は心臓を表していると言われるので、「災いが起こらないように」という願いが込められています。
ひなあられ
そして4つ目はひなあられです。
ひなあられはお餅に砂糖を絡めて炒った和菓子の1つで、ひな祭りの代表的な食べ物ですよね。
ピンク、白、緑、黄色の4色で作られていることが多いですが、この4色は四季を表しています。
昔、食べると夏の間健康に過ごせると言われていたお餅を原料として使い、4色に着色することにより、「1年中健康で過ごすことができるように」との願いが込められています。
なぜ?ひな祭りに雛人形と桃の花を飾るワケ
ひな祭りといえば、食事以外にも雛人形や桃の花を飾ります。
もちろん、食事と同様この2つにもきちんとした理由があります。
雛人形
まず、ひな祭りに雛人形を飾る理由ですが、これはひな祭りの由来にも関係しています。
もともとひな祭りは、古代中国で行われていた3月3日の上巳(じょうし)と言われる日に川で身を浄める習慣が基となっています。
それが平安時代に日本に伝わり、川で身を浄める習慣が川に人形を流して厄を払う「流し雛(ながしびな)」に移り変わりました。
その流し雛に、当時貴族階級の女の子の間で流行っていた「ひいな遊び(人形遊び)」に使われていた人形を使うようになり、最終的には川に流すのではなく「ひいな人形(雛人形)」として飾られるようになりました。
雛人形は「厄を払い、女の子が健やかに成長するように」との願いを込めて飾られているのですね。
桃の花
そして、なぜひな祭りに桃の花を飾るのかというと、桃の木は魔除け(邪気を払う)の力があるとされてきたからです。
ひな祭りの基となった古代中国の上巳の節句でも、桃の花を飾って無病息災を願っていました。
まとめ

女の子の節句であるひな祭り。
ひな祭りには、ちらし寿司やはまぐりのお吸い物、菱餅やひなあられなど、華やかな食べ物が並びます。
これらの食事にもきちんと意味があり、食べ物の1つ1つはもちろん、使われている材料や色にまで願いが込められています。
また、雛人形や桃の花を飾るのにもきちんと理由があるので、子供たちにもきちんと伝えていきたいですね。
日本の伝統行事ともいえるひな祭りには、親が子を想うたくさんの願いが込められています。
ひな祭りには心をこめて雛人形や桃の花、食事を準備して、女の子の健やかな成長を願いましょう!
ひな祭りには他にも一般にはあまり知られてないことがあります。
下の記事も参考にしてください。