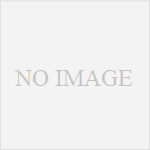お正月飾りを毎年飾って、処分をどうしたら良いか分からず、そのまま家にしまって保管している方もいるのではないでしょうか。
正月の間は、季節感が出て癒しの空間を演出してくれますが、時期が過ぎると飾っておくわけにもいきませんね。
本記事では、神社での処分の仕方などをご紹介しています。是非参考にして、溜まってしまっている正月飾りの扱いや処分などを進めましょう。
正月飾りの処分は神社で

まず、正月飾りを処分する時期についてですが、松の内の間は飾っておき、それを過ぎたら処分して良いことになります。
松の内とは、門松を飾ってあるという意味で、関東地方では元日から7日まで、関西地方では15日までの場合が多くあります。
また、松の内の期間は、神様に待っていただいている期間ともいわれています。
その期間は、地域によっても違うので、その土地での風習に従うのが良いでしょう。
処分して良い時期がきたら、どんど焼きが行われている神社でお正月飾りを持参し、お焚き上げをしてもらうという手順になります。
お焚き上げをしている日にちは、だいたい15日ですが、地域や神社によって日程が違っている場合もありますので、問い合わせた方が良いでしょう。
また、お焚き上げの日までは、家で保管しておくことになります。
その際は、きちんと紙袋に入れるなどして、大切に保管するようにしましょう。
正月飾りは歳神様をお迎えするという意味が込められているため、粗末に扱ってはいけないからです。
正月飾りを翌年も使って良いのか
本来なら、先に述べたように松の内の時期を過ぎたらお焚き上げをして処分するのが良いですが、近年では環境問題で燃やすという行為自体が難しくなっているので、正月飾りを再利用したいという方は多いのではないでしょうか。
最近では、翌年も繰り返し使える正月飾りもありますので、再利用しても特に問題ありません。
ただ、保管方法をきちんと把握して再利用を行うようにしてください。
わらなどのしめ縄は、ビニール袋に入れ、乾燥材と防虫剤を入れて、風通しの良い場所で保管するようにしましょう。
まとめ

このように正月飾りは、処分するには手間と手順がありますが、神様に待っていただいている、歳神様をお迎えするということからすると、ただゴミとして処分するわけにはいきませんよね。
正月飾りを翌年も使うのも良いですが、日本の伝統を大事にして本来の方法で受け継いでいきたいものです。
自宅で処分する場合は下の記事を参考にしてください。
また七草粥(ななくさがゆ)や鏡開きの由来については別記事で説明しています。
こちらも確認してみてください。
この記事が参考になったらシェアお願いします。これからも役立つ記事を書いていきます。