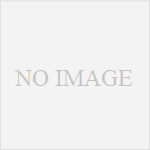正月飾りを処分するつもりが、お焚き上げの日に出し忘れたり、間に合わなかった場合、また、簡単に自宅で処分したい時、どうやって対処したらよいのでしょうか。
正月飾りを処分するつもりが、お焚き上げの日に出し忘れたり、間に合わなかった場合、また、簡単に自宅で処分したい時、どうやって対処したらよいのでしょうか。
無下にゴミとして処分するにはバチがあたりそうですよね。
ここでは、自宅での処分の仕方や神社で引き取ってもらう方法などをご紹介しています。是非参考にしてくださいね。
正月飾りの処分を自宅で行う場合

まずお清めをしてください。
お清めは、自分でしてもかまいません。
お清めの方法は、まず新聞紙など大きめの紙を用意します。
その上にお清めしたい正月飾りを置いて、お清めの塩を振ります。
塩の振り方は、左から右、中央の手順で3回行います。
これでお清めは終了です。意外と簡単ですね。
そして、分別としては、燃えるゴミになりますが、丁寧な扱いとして、新聞紙でくるみ、燃えるごみの袋に入れて出します。
この時、他のゴミと一緒にゴミ袋にいれてはいけません。
正月飾りとして歳神様の御迎えをしていただいたのですから、お清めしたとしても丁寧に対処するようにしましょう。
処分する時期としては、松の内の時期が過ぎてから処分するようにしましょう。
お焚き上げの日に出せなくても
自宅で処分するには忍びないと感じる方は、もしお焚き上げの日に間に合わなかったとしても、神社で引き取ってもらう方法もあります。
地域によって、また神社によって引き取ってくれるかどうか違いがありますので、問い合わせた方が良いでしょう。
長いと節分の時期まで受付してくれる神社もあるようですが、全く引き取りをしていない神社もあるようです。
節分にも忘れてしまっていたら、大きめの神社であれば、年間を通して引き取り受付してくれると思いますので、問い合わせて見つけるようにしましょう。
どうしてもそのような神社が見つからなかったり、遠すぎて持っていけないようなら、先に述べたように、自宅で処分する方法になります。
まとめ

近年では、環境の問題で燃やすという行為自体が難しくなってきているので、自宅で簡単に処分したいという方は多いと思います。
しかし、古来からの日本の伝統である神社でのお焚き上げをして、その煙と一緒に天にお帰りになるという意味で行う方法が本来のやり方ですので、できれば引き継いでいきたいものです。
自宅で処分するか、神社でお焚き上げをするかは、環境問題と伝統とのことを考えて、自分の気持ちに問いかけて対処するのが良いと思います。
神社でお焚き上げをする場合は下の記事も参考にしてください。
⇒ 正月飾りの処分は神社で行うのが基本です。知ってましたか?
また七草粥(ななくさがゆ)や鏡開きの由来についても気になってる方は確認してみてください。
この記事が参考になったらシェアお願いします。これからも役立つ記事を書いていきます。